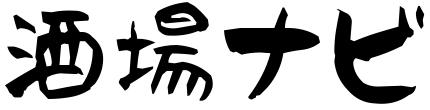秋田「からす森」私はもう秋田人ではない?ちょっぴり寂しい地元の夜
年末年始に地元へ帰る──そんな当たり前が、長い間ないことに気づいた。いったい私は何時から年末年始に帰郷していないかを思い出してみると……専門学生が最後。なんと約二十年間、年末年始を地元で過ごしていなかったことが判明した。念のために言っておくが、帰ることが嫌な訳ではなく、正月お盆に夏休みなどの〝人が混む〟時に帰るのが嫌なのだ。
ただ、さすがに私もいい年齢だ。たまには年寄り家族や姪っ子と、東京の日々を忘れてゆっくり過ごすのもいいだろう。そう思いついた2022年の暮れ、二十年ぶりに帰郷することにした。

雪の降りしきる我が地元秋田。おぉ……雪が積もった町を見ること自体、かなり久しぶりだ。晴れることのない鉛色の空、突如として吹き荒れる雪、指先の感覚が無くなるほどの寒さ……高校生まで暮らしていたことに驚きすら感じる過酷な世界だ。いや、当時はまったく普通のことだったこの環境が、もはや東京人としての身体が受け付けないのである。そう考えてみると、ショッキングなことだ。
そんな帰郷ならぬ〝異郷〟となってしまった秋田で、さらにショックを受ける出来事があった。

地元友人の誘いで、秋田一の繁華街『川反』のキャバレークラブへ行った年始の夜。横に付いた女の子に自分が秋田出身だと言うと、秋田弁で話してみてと言うのだ。私は、得意げに秋田弁を披露したのだが……
「それ、秋田弁じゃないよね」
「……えっ」
いやいやいやいや!何言ってんだこのオナゴは! ちょっと秋田美人……いや、かなり秋田美人だからって、私の訛りのどこが違うというのだ!
「そうそう、なんか変な訛りよね」
「お兄さんのはちょっと違う。エセ秋田弁?(笑)」
一緒にいる女の子、全員が納得していた。これは、ショックだった……関西出身の酒場ナビメンバーのイカやカリスマジュンヤに、秋田弁をちょっと喋ろうもんなら鼻血が出るほど笑ってくれるというのに……急に恥ずかしくなった。
変わってしまったのは、身体だけではなかったのだ。私はこの二十年という東京生活で、愛する地元の言葉まで忘れてしまっていたのである。

その後も、いっちょ前に胸元を覗いたり、カラオケなんかをしたりして愉しむことは出来た……が、やはり女の子らが言っていた〝エセ秋田弁〟という言葉がずっと引っかかっていた。だから、東京のカラオケなら必中必殺で盛り上がる吉幾三の『俺ら東京さ行ぐだ』は、間違って唄うことはなかったのである。

さらに、次の夜が来た。
キャバクラでの二日酔いを若干残しつつも、やはり酒場には行っておきたい。場所は決まっている。秋田に帰ってきたら必ず行くあの名酒場である。

降り積もった雪が、何とも東北らしい酒場の情緒を醸し出している。『からす森』は秋田駅から歩いてすぐにある老舗酒場だ。

名前が変わっている。そもそも〝カラス〟自体のイメージがよろしくないのに、さらに〝森〟にしちゃったっていう。酒場の名前は、たまにこんな皮肉めいたものがあるから面白い。それはそうと、寒さで指先が痺れてきた。早く中へ入ろう。
「あい、いらっしゃーい」

おっほう、何度見ても絶景だ! 大将が迎える縦長の細いコの字カウンター、左右には渋く照りを放つテーブル、店内にせり出している厨房の感じは、まるでかつての『山田屋』のようでもある。
「へば、こさ座ってけれす」

秋田弁強めの男子店員が、カウンター席へ案内してくれた。アクリルボードが邪魔ではあるが、やはりここのカウンターからの眺めは最高だ。特に冬なんかは、寒くて皆で身を寄せ合って飲っているのがたまらない。
「んだがらなぁ~」
「なーんと、寒んびくてヤメなるわ」

私の両側で既に飲っていた先輩らも、どぎつい秋田弁だ。嬉しいというかなんというか、この状況に〝落ち着く〟という感情が、自分がまだ秋田人なのだという証なのかもしれない。よし、酒ッコ貰うべがな!

悴んだ手に、冷えたビール瓶をしっかりと握り、小グラスへトットット……オットット、これで準備完了。さぁさぁさぁ、新年に相応しい酒場で祝杯だ。

グビッ……カラッ……スヌッ……、マァァァァッすったげウメなぁぁぁぁ!! 初詣はまだであったが、こりゃおみくじで大吉を引いた気分のようだ。
「あい、コレな──
こっちも、あい──
うんめがらな!」

焼き場にいた大将が、焼き立てのやきとんをカウンターの内側から客へポイポイと振り分けていく。秋田弁は「はい」を「あい」にしがちである。やきとんはマストで頼むとして……おっ、これがいい。
「すいません、野菜サラダあるすが?」
「あるす、んでもちょど時間かがるす」
「なも、いすよ」
秋田弁でお願いしてみるが、昨夜の件もあって引け腰だ。それはそうと、酒場が出すサラダは結構おいしいものが多いのをご存じだろうか。ここのサラダは食べたかことがなかったので、待っている間に他の料理をつまんでいよう。

きたきた、ここでは必ず『じゃがバター』を頼むのが私流。太っちょメークインはホッカホカの湯気を上げ、とろぉりと角バターを蕩かしている。こんなもん、絶対うめぇに決まっている。

ぽくぽくとしたイモの旨味が口の中でホロホロと崩れ、濃厚バターと共に舌に消えていく。本当においしいので、いつも追加注文しようか迷ってしまう。
「あい、カシラどナンコヅ!」

と、大将が『カシラ・ナンコツ』をポポイと小皿に並べた。今でこそ〝やきとん〟なんてものは当たり前の存在だが、秋田にいた高校生までの中では、決して当たり前の存在ではなかった気がする。いや、やきとんの存在すら知らなかった。そんな秋田のやきとんを、こうして目の前にするという巡り合わせ……なんだか、酒場好きでよかった。

カシラは小ぶりだがムチムチとした歯触りが極上で、ひとつだけ〝アブラ〟になっている。淡白なカシラのシメに、ボッテリとしたアブラの味わいがいい。ナンコツはコリコリの食感に加えて、ナンコツに引っ付いた肉の旨味が、ジワジワと口中を溢れさせる。秋田のやきとん、うめぇじゃないか。

カウンター向かいで、かなりお年を召したマダムが『ウィンストン』を爆吸いしている。
「熱っぢーやづ、けれ」
「酒だべ? ちょっと待っでれ」
マダムはウィンストンを灰皿で消しながら、大将に熱燗を頼んだ。〝熱っぢーやづ〟という、とてつもないネイティブな訛りに懐かしさを覚えつつ、私の方は料理の〝熱っぢーやづ〟を頂くことにした。

やはり〝熱っぢーやづ〟といったら『湯豆腐』は外せない。さらに秋田酒場の湯豆腐は、かなり具沢山なところが多いのがうれしい。ネギ、春菊、しめじ、カマボコ、そして主役の豆腐とやはり多い。そして鍋の真ん中に鎮座しているのが、ほぼ醤油原液といっていい、かなり味の濃い付けツユである。

秋田の湯豆腐では当たり前なのだが、ツユの中には〝鰹節〟が沈んでいる。このほぼ醤油と鰹節の合わさった〝真っ黒なツユ〟は酒場ではもちろん、家庭でもお馴染みなのだ。出汁を重んじる京都人なんかがこのツユを舐めようもんなら、目から火花が出るんじゃないだろうか。

この真っ黒なツユに、豆腐をジャブジャブに染み込ませて食べる……ああウマい、ウマ塩っぱい! この単刀直入な濃い味、〝しょっぺくてウマい〟というのは、秋田の味付けでは最上級の誉め言葉だ。豆腐に、ネギに、しめじに〝ガツン!〟とした醤油味、私の体に宿る根本的な味覚であることは、間違いないのである。

結局、はじめに頼んだ『野菜サラダ』は届かなかった。まぁ単に忙しいので注文が通ってなかっただけなのだろうが、やはり私の〝エセ秋田弁〟が通じなかったからか、それとも二十年も年末年始に帰らなかった罰なのか……そんなネガティブに浸っていると──
「あい、今年もよろしぐ!」

大将が〝お年賀〟を、客ひとりひとりに配り始めたのだ。手ぬぐいと厄除けストラップである。物を貰った喜びよりも、この酒場の、この秋田の酒場の〝一員〟として認めてもらえていることが嬉しかった。もはや心身ともに〝エセ秋田人〟なのではと、疑心暗鬼していた私にとっては何よりの品だ。お年賀を受け取った客のひとりが、大将に言った。
「お年玉は入ってねんだがー?」
「なに言っでらー!」

身を寄せ合うカウンターは、静かな笑いに包まれた。それはカラス達が喚くような大きな笑いではなく、まるで深々と降る雪に浮かぶ、小さな酒場の灯りのように。
二十年という年月で、私は雪を珍しがり、秋田弁を上手く喋ることができない〝東京からのお客さん〟になってしまった。ちょっぴり寂しいが、また帰った時も自分がまだ秋田人であることを、この酒場で確かめたい。
からす森(からすもり)
| 住所: | 秋田県秋田市中通4-11-3 |
|---|---|
| TEL: | 018-835-5906 |
| 営業時間: | 17:00~22:00 |
| 定休日: | 日 |