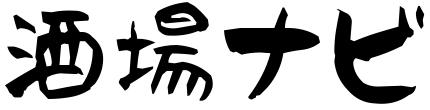【続】新宿「番番」新宿三大酒場 その1
「もしもし、味論くん? ワイ、同じバイトのもんやけど」
「はぁ、はじめまして……」
約二十年前、家にいるとFOMAの携帯電話に知らない電話番号の着信があった。電話に出ると、どぎつい関西弁の男が突然バイトのシフトを代わってくれと言ってきたのだ。代わってくれもなにも、この関西人は一体誰なのか。というか、この時点で私はまだバイト二日目だった。
「シフト見たら火曜日休みにしてるやん? 何か理由あるん?」
「いや、特にないですけど……」
「ほな、ワイの土曜日と代えてーや。ええやろ?」
「はぁ……いいですけど」
すごく、嫌でしたねぇ……なんてガサツなんでしょう。東北出身の私は、特に関西人と接点が少なく怖かったことを覚えている。訳も分からず承諾して電話を切った。どんな人なんだろう、ちょっと会うのが嫌だなぁ……この後の出勤が少し憂鬱になったのを覚えている。

そんなバイトの始まりだったが、結局なんと三年以上を勤めることになる。まぁ〝勤める〟なんて行儀のいいものではなく、ほとんど〝遊び〟のようなものだった。それは新宿アルタ裏にあった24時間営業の漫画喫茶で、夜の10時に出勤して、溜まっている食器を洗い、一緒にいるバイトの先輩と駄弁って、あとは交代が来る朝8時まで漫画を読みながらレジをやる。仕事はこれだけ……いや、本当にこれだけだった。
もちろん、こんなのは仕事とは言えないが、これは私だけではない。私は一番後輩だったので、その業務内容は諸先輩方から見習ったのだ。言うまでもなく、この先輩方も滅茶苦茶だった。そこのところを詳細に書きたいところだが、時効とはいえ、ひょっとすると逮捕されるかもしれないでの止めておくが、その中でも特に狂っていたのが〝イカ〟という先輩だった。

そう、酒場ナビメンバー、あの彼である。
「おい味論、今日は鍋やるで」
「おっ、いいですね」
夜の10時を過ぎると店長が帰るのだが、そこからが本番の始まりだ。イカと一緒の深夜勤務の時は、大抵は近くのスーパーで惣菜を買ってきて、そこから店の奥にある台所で〝晩酌〟を始める。もちろん、営業中にである。この日は、自宅からガスコンロと鍋を持ち出してタラ鍋をするという。鍋が仕上がるまで、ビールサーバー(客用)からビールを注ぎ乾杯。鍋を突きながらほろ酔いになってくると、交代で、しかも客席で仮眠を取るのだ。こうなると、客なんかはそっちのけになるから、何度も食い逃げに遭うのである。

他にも焼鳥や回転寿司の折詰を買ってきてよく食べた。こんなのが毎日で、今では……いや、当時でも考えられないバイトだった。

ちょうどこの頃、はじめて新宿の大衆酒場というものに触れたのが、そのバイト先からすぐ近くにあった『番番』だった。その当時私は二十代前半、今みたいに渋いだとかカウンターがどうとかなど皆無だったが、イカは当時から大衆酒場好きだったようで、休みの日に連れてこられたのだ。

はじめては、何を飲んだんだっけなぁ……レモンサワー、いや、ハイボールだったかな? とりあえず久しぶりの番番は、ウイスキーハイボールから頂こう。

お代わりをすると、グラスにレモンを追加して何杯飲んだか分かるタイプ。こんなのも、ここが初めてだったな。

そうそう、ここは酒が濃いんだよ。ここで飲ると、いつも記憶が飛んでいる気がする……そういえば、初めて〝酒で記憶を飛ばした〟というのも、イカに原因があった──
「お前って、めっちゃ酒強いで」
「え、そうですか?」
バイト先で、夜食という名の〝晩酌〟にも慣れた頃、イカから言われて気が付いたのは、どうも私は酒が強いことだった。ただその当時はあまり酒を飲まず、飲んだとしてもビールを数杯程度だったので、自分が酒に強いかなどまったく意識したことがなかった。バイト先での〝晩酌〟を始めるようになり、イカがそのことに気が付いたのはよかったが、ある日、イカの悪ノリが始まった。

「お前なら、ウイスキーもいけんちゃう?」
「あー、飲んだことないっすね」
酒の飲み方を一切知らない私に、イカは持ってきたウイスキーをジョッキに並々と注いで飲ませたのだ。ストレートどころの話ではない、天龍源一郎の飲み方と一緒だ。今でこそ「飲めるか!」と言えるが、酒を知らない私はそのまま半分ほど飲んだ。

「甘い! ウマい!」
「せやろ! もっと飲めや!」
……ハッと気が付くと、私は客席のソファーで目を覚ました。頭が痛い……ウイスキーを飲んだまでは覚えているが、そこから記憶は皆無だ。こんなことは初めてだ……厨房に居たイカに話を聞くと仰天した。

その後、ジョッキのストレートを三杯飲んだところで、私はイカの言うことをなんでも聞くようになったのだという。「牛のモノマネせーや!」と言われた私は、そのまま「モーッ!」と牛の真似をして、歌舞伎町の方へと足り去っていたらしい。その後、歌舞伎町を(おそらく)徘徊したあとに、店の前に出ていた屋台で飲んでいたのを、イカが引き取ったらしい。それが私の初記憶飛ばしになった──

くぅぅぅぅ、馬刺しうんめぇなぁ。赤々とした新鮮そのものの身には鹿の子模様のサシが入り、見るからにウマい。滋味深い脂の香り、とろりと蕩ける赤身の刺身は、馬肉ならではのおいしさだ。

あっ、赤身の刺身でもひとつ思い出した──
その日、いつも通り夜10時にバイト先に到着すると、イカが築地で〝凄いものを手に入れた〟と豪語してきた。それを、もう一人のヤンチャな先輩と三人で〝晩酌〟しようというのだ。店長が帰り、店の冷蔵庫に入れておいたものを出してきてビックリした。なんと皮付きのマグロの塊だったのだ。

とにかくめちゃめちゃデカくて、どうやってこれを捌くのか……イカとヤンチャ先輩の二人で、厨房にある包丁を使って解体を始めるのだが、なんといっても普通の包丁だ。普段、客に出すレモンティーのレモンを切るぐらいの能力しかない。それでも時間をかけて、何とか刺身状にすることが出来た。一応言っておくが、これは漫画喫茶のバイト中のことだ。
大振りに切ったマグロの赤身を、狭い厨房のちょっとしたテーブルの隅で立ちながら食べ始めた。それを酒で流し込む光景は、完全に狂った立ち飲み屋でしかなかっただろう──

おほっ! きたきた、番番のやきとり! ここで焼鳥を食わない手はないでしょう。ツクネ、ネギマ、正肉、砂肝……好きなものだけを好きなだけ頼む。ツクネの軽めのニラがいい、ネギマの塩加減ったら素晴らしい。正肉のプリッとした歯ごたえが小気味よく、砂肝はカラシたっぷり目でかじりつくのが最高だ。やはりここの焼鳥は、新宿で一番じゃないかと確信している。

一番……そうだ、新宿で一番といえばあんなこともあった──
そのバイト先の建物は、どうやって認定されたのか分からないが、当時新宿で一番〝不衛生〟な店だったらしい。しかもイカ曰く、七年連続だったという。新宿で一番なら、おそらく日本で一番不潔な店だったんじゃないだろうか。そういわれてみれば、厨房ではいつも「チューチュー」とネズミの鳴き声が聴こえていた。

客に「ネズミ! そこ、ネズミいる!」と叫ばれても「えっ、そんなのいませんよ!」と何度とぼけたことか。慣れというのは本当に怖いもので、この不衛生極まりないバイトを普通に感じていたのだ。
〝えっ!? ちょっと、今なに捨てました!?〟
〝なんでもない! 見んでええわ!〟
〝いや! なんか出てますって!〟
〝出てるくらいが丁度ええねんて!!〟

──それこそ全部語ったら記事ひとつ分どころか、特殊なコンテンツを作れる自信がある。ただ、誰がそんなもんを見るのかという話だが。
改めて、本当にめちゃくちゃなバイト、とんでもない人物と出会ってしまった。同じ新宿の地下だからだろうか、この酒場に来るとなんとなくその当時のバイトのことを思い出すのだ。

そんなバイトを経ても、ほとんどがまともな父親や母親になれているが、あとはミュージシャンや俳優、海外で壁画アーティストなんてのもいる。そして、酒場めぐりだけで生きていことする者が二名……
ある意味、今もあのバイトの途中なのかもしれなと苦笑い、これからもこの濃い酒を飲み続けるのだ。

元記事
番番(ばんばん)
| 住所: | 東京都新宿区歌舞伎町1-16-12 |
|---|---|
| TEL: | 03-3200-9354 |
| 営業時間: | 17:00~21:00 |