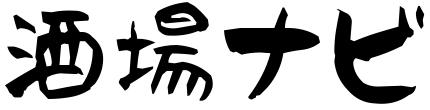吉祥寺「いせや 公園店」人生初めての大衆酒場にて
出会いがあれば、別れもやってくる
四月というのは、特にこの東京において様々な人の出入りがあって、進学のための上京や、転勤で地方へ異動など、どっと人の流れが生じる時期なのだ。今年も新コロの影響があったので、例年ほどの人の流れは感じなかったものの、それでも通勤電車には人が増えた。
そんな私も二十年以上前は、地元の秋田からこちらへと移り住んできた組だった。

専門学校に入りし、初めての登校日は東京の電車の乗り方が分からず遅刻をした。その日はクラス全員の自己紹介から始まり、私は緊張しながらも流暢な秋田弁で、若干の笑いを取ることができた。自分の番が終わり、のんびりと人の見ていると、やけに声の小さいヤツがボソボソと自己紹介を始めた。そりゃ恥ずかしいのだろうが、自己紹介なんて、ほとんどのヤツは聞いちゃいないのだ。そんなことを思っていると、近くから声がした。
「あいつ、声小っちゃくね?」
それは、通路は挟んだ隣席からだった。髪が緑色で、少しヤンチャな感じの男。こいつが『S』だった。Sは、明らかに私を見て言っている。……エッ、俺? と一瞬怯んだが、ここは東京モンに舐められてはいけないと、スカした口調で返した。
「あぁ、うん。小さいよな」
放課後、Sと一緒に帰ることになった。途中で、歌舞伎町の入口にある『PRONTO』へ寄り、二人で色々な話をした。Sは生粋の東京人で、出てくる言葉ひとつひとつが、とにかく真新しく、だけどそれを感づかれるのもシャクで、必死に話を合わせていた。なんせ私は、喫茶店に来ることすら、生まれて初めてなくらいだった。
そこから気が付いたら〝親友〟で、酸いも甘いも、本当に色々なことを一緒に経験したが、ここには100分の1だって書ききれない。そんな、書ききれない思い出の中に、最近またひとつ、ある出来事が追加されたのだ。
〝仙台へ転勤することになった〟
三月の終わり、Sから突然のLINEだった。えっ、仙台……仙台って、あの東北の? はっ、なんで? おいおい、私が東北から上京して、今度はお前が東北に行くのか?……そんなことある!? なかなか話を飲み込むことが出来なかったが、どうやらそういうことらしい。
出会いがあれば、別れもやってくる
こんなにも、その言葉を近しく感じたことはなかった。すぐにでも詳しい話を訊きたかったが、LINEや電話で済ませられる話ではない。
〝まじで? とりあえず飲むかー〟
私は、二十年前に初めて声をかけられた時のように、スカした口調で返信した。その夜は眠れなかった。どう考えても、現実味が沸かないのだ。ただ、その悶々としたベッドの中で〝アイツと絶対に行こう〟という場所は決まっていた。
****

数日後、私とSの姿は吉祥寺に在った。この住みたい街ランカーと、若者に溢れるフレッシュな街には、ある意味似つかわしくない老舗酒場がある。

『いせや 公園店』
2013年に大改装してからも、Sと何か大事な話をする時には、決まってここへ来るのだ。今日も、間違いなくここに来ようと決めていた。なんなら東京で……いや、生まれてからはじめて〝大衆酒場〟と触れ合ったのは、間違いなくこの酒場だ。そこで何度となく、恋、夢、仕事、Sの結婚報告も、ここで訊いた、私の知るすべての酒場の中で、ここまで思い入れのある酒場ない。

「何人スか? じゃあ地下で」
改装前の面影は一つもないが、ぶっきらぼうな口調の店員さん達は変わらない。いや、これがいいのだ。接客の良いいせやの店員なんて、それはいせやではないのだ。

あぁ、お洒落だねぇ……もう、改装前のものとはまったく違うものになってしまった。本当にボロボロだった……吹き抜けの広い店内には、ガタガタでギトギトのテーブル、二階に上がる異常に急角度の階段、座敷はボールが転がるほど傾き、男女兼用トイレの小便器は外から丸見えだった頃が懐かしい。まぁ、そんな事を言ったってしょうがないのだ、という会話を、毎回Sとしながら席につく。

「瓶ビールグラス2つと、中華ガツください」
席に座れば、私は何もしない。注文から何からSが全部やってくれるのだ。はじめに頼む瓶ビールと中華ガツ、私はこの店で、これ以外の切り出し方を知らない。さあ、始めましょうか。

グビ……グビ……グビ……うんめぇ。祝杯……なのかは分からないが、まずは二人でグラスを空ける。これはもはや、ここでの儀式だ。間髪入れずに、次の儀式が始まる。

『自家製中華ガツ』
〝ガツ〟という存在だって、ここではじめて知ったはず。ただ、その後に出会うガツの中でも、ここのは格別。絶妙な茹で加減で、柔らかいような歯ごたえがあるようなガツに、カラシの効いた酢が最高に合う。何十回食べても、毎回ウマい。

『やきとり(タレ)』
いせやといったら、やきとりは外せない。元々は80円均一だったが、一本90円になってもサイズは変わらず、どれも大振り。サラリとしたタレは、見た目より味がしっかりとして、何本だってイケる。

新コロ関係なく、昔から店先の焼き場でテイクアウトをしており、いつだって客が並んでいる。何年か前に、この焼き場の様子を映した動画を、何度も観ていたことを、ふと思い出した。
「すんませーん、シューマイください」
Sが、いつも通りのコールをする。とりわけ、このコールをする時のSの表情は、自身に満ちあふれている。

『手作りシューマイ』
特にこのシューマイに関して、すぐに手を出すことは許されない。ここからSの〝調整〟が始まるのだ。

まずは、醤油をサッ振り回す。もちろん、適当ではない。その日の気温、湿度、なんなら気分もあるようだ。そこからさらに〝酢〟を掛ける。もちろん、適当ではない。酢が嫌いな人だっているだろうが、Sには関係がないことだ。

最後にシェフ自ら切り分け、カラシをたっぷりと付けて、やっと「召し上がれ」となるのだ。ぎゅうぎゅうと詰まったひき肉から、じゅわりと肉汁が溢れる。そもそも、いせやは肉屋なので、肉に関して心配無用のウマさなのだ。そこへ、Sこだわりの調整が入ると、なんかだか悔しいが、二倍くらいウマくなるのだ。

肉々しい食べ応えに、絶妙な酢醤油の加減が、うーん、やっぱりうめぇ。Sには言ったことがないが、初めてこうやって食べさせられて以来、私は酒場だろうが家だろうが、シューマイを食べるときは必ず酢醤油にカラシをと決めている。
それを食べる度に、〝いせやとS〟をアタマのどこかに過るのが、ごく当たり前だった──
「しかし、本当に急だな」
「少なくても、数年は帰ってこれないっぽい」

数年って……そんなもん、お前が東北人になっちまうじゃねえか。
今日会うまで〝実は行かなくてもよくなっているんじゃないか……?〟などと淡い期待をしていたが、いよいよ現実の話になってきた。今までは会おうと思えば二十分もあれば合流できる場所にお互い住んでいたが、今後は新幹線で二時間以上かかる。これは、遠いぞ。
「嫁さんとも、かなり話あったよ」
「そりゃ二人とも、縁も所縁もない場所だしなぁ……」
奥さんも東京の人間だ、葛藤しかないだろう。そんなコイツに、四十代のオッサン同士として、なんと激励してやればいいのか……ほろ酔いのアタマで、ふいに浮かんだ思い出を言葉に出した。
「でもさ、専門学校でお前が俺に声かけてくれたじゃん?」
「ああ、そうだったな」
「もし、あの時に声かけてくれなかったら、俺の人生、ちょっと変わって……」
「……」
「……た、かもな」
「……」
「……」
まてまて!! そんな深い意味で言ったつもりじゃないのに、泣きそうになったじゃねえか!!……Sも俯いている。いくら思い出の酒場でも、オッサン二人で泣くのは恥ずかしい。この酒場に、そんなのはいらないって!
「いや、だから、まぁ……今度はお前が東北に行くわけじゃん?」
「……うん」
「俺の時みたいに、お前に声をかけてくれる人がさ……」
「……」
「……いれば、いいよな」
「ああ、そうだな」
「……」
「……」
あっ! だめだ、もう出よう! ここから出よう! 大至急出よう!
「そろそろ! 出ようかぁ!」
「おう! お会計くださーい!」

激励なんて、できるもんじゃない。ただ親友ですからね、やはり意思疎通するのでしょう。お互い無暗に大きな声となって店員さんを呼んで会計を済まし、そのまま変なテンションで思い出の地を後にしたのだった。
私はSの前では、絶対に泣かないと決めている。しかしまぁ、今回は危なかったぜ……。
****

それからさらに数週間後、Sを見送るために私は東京駅へ訪れた。もう言い残すことはない、先日のいせやで済ませている。ホームの待合室で軽くしゃべり、もちろん、お互いに涙なんて流すことなく、湿っぽくなく、卒なく、Sが乗った仙台行きの新幹線を見送ったのだ。
〝またな、次は仙台で飲もうぜ〟
帰りの中央線快速に乗って暫くすると、車内案内板に、
〝吉祥寺──27(分)〟
というのが見えた。
その表示が、なぜか懐かしく感じて、「あぁ、やっぱりこの前、いせやで飲んでよかったな……」と思うと、やっぱり涙があふれてしまった。
いせや 公園店(いせや こうえんてん)
| 住所: | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-15-8 |
|---|---|
| TEL: | 0422-43-2806 |
| 営業時間: | [火~日] 12:00~22:00 |
| 定休日: | 月曜日 |